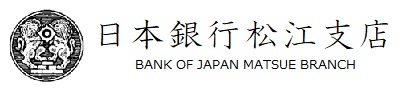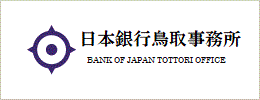支店の歴史
沿革
| 大正7年(1918年) | 松江支店開設(松江市殿町、木造) | 昭和13年(1938年) | 松江支店改築(2代目営業所、松江市殿町、鉄筋コンクリート造) | 昭和20年(1945年) | 旧日本勧業銀行鳥取支店内に鳥取駐在員事務所開設(翌年鳥取事務所に改称) | 昭和28年(1953年) | 山陰合同銀行鳥取支店内に鳥取事務所移転 | 昭和47年(1972年) | 集中豪雨(宍道湖が氾濫)の発生に伴い、地下金庫に浸水被害が発生 | 昭和56年(1981年) | 松江支店移転(3代目営業所、松江市母衣町<現在地>)、銀行券自動鑑査機導入 | 昭和63年(1988年) | 日本銀行金融ネットワークシステム(日銀ネット)稼働開始 | 平成2年(1990年) | 機構改編:業務課制スタート | 平成3年(1991年) | 機構改革:4課制(営業・発券・業務・文書)から3課制(総務・発券・業務)へ | 平成12年(2000年) | 松江市が旧松江支店店舗を改修し、「カラコロ工房」を開館 | 平成20年(2008年) | 松江支店開設90周年 | 平成30年(2018年) | 松江支店開設100周年 |
|---|
日本銀行松江支店の店舗
松江支店は、地元銀行の利便性向上と、銀行券流通の順便化を図るため、大正7年(1918年)3月に開設されました。全国では14番目、中国・四国地方では広島支店に次ぐ2番目の支店開設でした。初代の松江支店は、木造平屋建ての本館と、レンガ造りの食堂・宿直室、金庫で構成されていました。支店周辺は、明治から大正にかけて、山陰の金融の中心地として、地元銀行が立ち並び、「松江のウォール街」と呼ばれていました。
本館は外壁に化粧レンガを貼ったレンガ造り風の洋風建築でした。しかし、初代建物は、宍道湖畔の軟弱な地盤に建築されたことから、一番重い金庫が沈み始めたため、当時の場所のまま改築することとなりました。

初代店舗(松江市殿町) 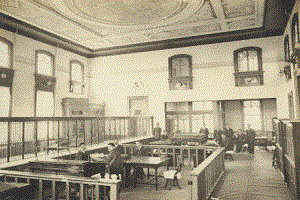
初代店舗の営業場
二代目の松江支店は、日本銀行で初めての現地改築を行い、昭和13年(1938年)3月に完成しました。多くの銀行建築を手掛けた長野宇平治が設計し、店舗は鉄筋コンクリート造り、地上三階、地下一階で構成されていました。山陰では初めてエレベータが設置された本格的なモダン建築として話題を呼びました。現在は松江市に譲渡され、当時の風情をそのままに改修され、「カラコロ工房」として、松江市民や観光客の方々に親しまれています。
昭和47年(1972年)、集中豪雨に伴う宍道湖および店舗前の京橋川の氾濫により、地下金庫に浸水する事態が生じました。このため、場所を移転し、新築を行うことになりました。
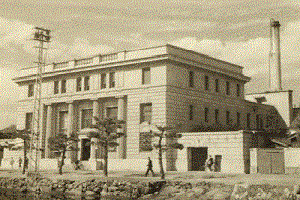
二代目店舗 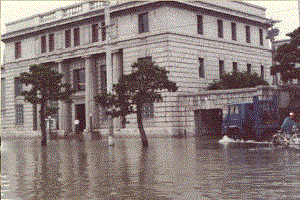
集中豪雨による冠水
昭和56年(1981年)4月に母衣町の現店舗に移転しました。新店舗の外観は、松江に残る武家屋敷や出雲大社をイメージして、設計されました。前庭の植え込みには県木のクロマツが、建物外周には地元産の大根島石の石垣が巡らされています。
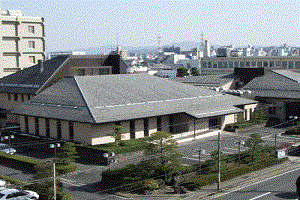
三代目の現店舗(松江市母衣町)