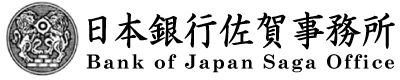所長から「ちょっと一言」
2026.2.4
金融経済概況(2026年冬)を公表しました
2月2日に、佐賀県の金融経済概況(2026年冬)を公表しました。景気の全体判断は、前回(2025年秋)と同様、「横ばい圏内の動きとなっている」としました。 項目別では、住宅投資の判断を「弱めの動きとなっている」に引き下げた一方、生産の判断は「横ばい圏内の動きとなっている」に引き上げました。その他の項目の判断はいずれも不変で、個人消費は、物価の上昇を背景に、値頃感のある商品への需要集中や不要不急の商品(例えば衣料品等)の買い控えといった、節約志向の動きがみられていますが、年末年始等のハレの日需要は堅調に推移するなど、所得が改善する下で、全体としては底堅い動きが続いています。また、公共投資や設備投資も高めの水準にあります。 この間、米国の通商政策や中国関連の供給制約・渡航自粛要請等の影響については、現時点では、引き続き限定的であるとみています。 今後も、各国の通商政策等の影響を受けた海外の経済・物価動向や、その下での企業の賃金・価格設定行動、政策金利引き上げの影響等を丁寧にフォローしていきたいと考えています。
所長から「ちょっと一言」一覧
2026.1.7
日本銀行佐賀事務所は今年開設80周年です
新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。 私ども日本銀行佐賀事務所は、お陰様で、今年2月18日で開設80周年を迎えます。当事務所は、終戦から間もない1946年(昭和21年)2月18日、国内にある14事務所のうち10番目の事務所として、当時の佐賀中央銀行佐賀支店(元佐賀銀行呉服町支店)内で業務を開始しました。その後、幾度かの移転を経て、現在は佐賀銀行本店内で業務を行っています。事務所長も、私で34代目となります。 日本銀行の国内事務所のほとんどは、終戦前後の1年余りの間に開設されており、その背景には、当時、交通・通信事情が悪化する中で、日本銀行と地方行政機関との連絡を密にするなどといった目的がありました。 今後とも、日本銀行券の安定的な供給をはじめ、金融経済動向に関する情報収集や情報発信、金融経済教育の支援など、佐賀県の皆様のお役に立てるよう、しっかりと取り組んで参ります。引き続きよろしくお願いします。
2025.12.3
J-FLEC(ジェイフレック)をご存じですか?
皆様、J-FLEC(ジェイフレック)という組織をご存じでしょうか?正式名称は「金融経済教育推進機構」といい、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、2024年4月に設立された認可法人です。中立・公正な立場から、国民の皆様に広く金融経済教育を届けることを目的としており、日本銀行や各都道府県の金融広報委員会等とも連携しながら、様々な活動を展開しています。 例えば、全国の企業や学校等にJ-FLECが認定する講師(J-FLEC認定アドバイザー)を派遣し、出張授業を行ったり、社会人、教員、親子向け等のお金に関するイベント・セミナーを各地で開催しています。また、金融経済教育研究校の指定を通じた学校教育の支援や、J-FLEC認定アドバイザーによるマネープランに関する個別相談、ウェブサイト・SNSを通じた様々な教材・コンテンツ(動画も多数あります)の提供にも積極的に取り組んでいます。 佐賀県の皆様にも、まずはウェブサイト・SNSを手始めに、J-FLECが発信する様々な情報や活動にぜひ触れてみていただければと思います。
2025.11.6
金融経済概況(2025年秋)を公表しました
11月4日に、佐賀県の金融経済概況(2025年秋)を公表しました。景気の全体判断は、前回(2025年夏)に引き続き、「横ばい圏内の動きとなっている」としました。物価上昇の影響(低価格商品へのシフトや買い入れ点数の抑制、メリハリ消費等)はみられていますが、これが一段と強まっている状況にはなく、所得環境が改善する下で、個人消費は全体として堅調を維持しています。また、公共投資や設備投資も高めの水準にあり、全体として「横ばい圏内の動き」が続いていると判断しました。 米国の通商政策等の影響についても、現時点では、引き続き限定的なものにとどまっているとみています。 先行きについては、物価上昇の影響を引き続き注視するほか、米国通商政策等を背景とした世界経済の動向変化や、その下での企業収益、企業行動(設備投資、賃金・価格設定等)の変化について、丁寧にフォローしていきたいと考えています。
2025.9.30
佐賀県における日本銀行券の発行・管理
私ども佐賀事務所では、佐賀県における日本銀行券(お札)の発行・管理に関する業務を行っています。具体的には、県内の金融機関に銀行券を円滑に供給するとともに、使われて戻ってきた銀行券を回収する業務です。 供給では、福岡支店から輸送されてくる銀行券を専用の金庫で保管し、金融機関に払い出していきます。回収時は、同金庫にいったん保管し、その後、福岡支店に輸送します。回収した銀行券は、1枚1枚チェック(鑑査)し、流通に適するものだけを再び世の中に送り出していきます。 当HPでは、毎月、佐賀県における銀行券の受払高を公表しており、2024年度の支払高は計4,238億円、受入高は計324億円に及んでいます。日本銀行と金融機関との間での銀行券受払高は、金融機関における現金関連事務の効率化(現金の繰り回し利用等)や、キャッシュレス化の進展もあって、やや長い目でみると縮小傾向にあります。しかし、上記の数字にも表れている通り、現金使用へのニーズは引き続き高いものがあります。当事務所では、佐賀県の皆様に安心して日本銀行券を使っていただけるよう、今後とも努めて参ります。
2025.9.3
日本銀行の企業ヒアリング
佐賀県の経済調査は、福岡支店営業課のスタッフが中心となって行っていますが、県内企業の経営幹部の皆様との面談には、私もできるだけ同行させていただいています(昨日も、1社面談をさせていただきました)。面談では、主に①足元の業況、②先行きの見通し・事業計画、③金融政策等への要望、といった点をお伺いしていますが、統計データにはまだ表れていない直近の変化や温度感を含め、地域経済の最前線の実情を把握させていただく貴重な場となっています。佐賀・福岡だけでなく、日本銀行の全国のネットワーク(32支店・12事務所)を通じて、こうした生の声に職員が直接触れさせていただくことが、日本銀行の経済調査・景気判断の支え、強みとなっています。 新人当時、大分支店でこうした経済調査に初めて携わり始めた頃、上司からは「日銀の調査は『足で稼ぐ』調査だ」と、現地・現場に赴いて直接話を聞くことの重要性をよく教えられました。これからもこの精神を大事にしていきたいと思います。企業の皆様にはご負担をおかけしますが、よろしくお願いします。
2025.8.5
金融経済概況(2025年夏)を公表しました
8月1日に、佐賀県の金融経済概況(2025年夏)を公表しました。景気の全体判断は、前回(2025年春)に引き続き、「横ばい圏内の動きとなっている」としました。物価上昇の影響(低価格商品へのシフト、メリハリ消費等)はみられていますが、所得環境が改善する下で、個人消費が全体として堅調を維持しているほか、公共投資、設備投資も高めの水準にあり、全体として「横ばい圏内の動き」が継続していると判断しました。 米国の通商政策の影響が注目されるところですが、現時点では、具体的な影響は限定的とみています。もっとも、先行きの不確実性はなお高い状況にあります。先般の日米間の関税交渉の合意を受けて、企業の行動(事業計画等)が具体的にどのように変化していくのか、といった点を始めとして、今後の動向を注視していきたいと考えています。
2025.7.15
支店長会議に行ってきました
7月10日に東京・日本橋の本店で日本銀行の支店長会議が行われ、私も出席してきました。支店長会議は年4回行われ、国内支店長や海外の拠点長から各地の金融経済情勢が報告されます。今回も、米国通商政策や物価動向等の影響を始めとして、各地の様々な「生の声」が紹介されました。 日本銀行のHPでは、「各地域からみた景気の現状」として、そのエッセンスが紹介されていますので、ぜひご覧になってみてください。さらに、支店長会議に向けて、各支店の調査スタッフが収集した情報(各地の企業等の皆様から直接お伺いした貴重なものです)をより詳細・具体的に整理したものとして、「さくらレポート」(ピンク色の表紙のため、こう呼ばれています)があります。これも日本銀行のHPに掲載されていますので、お時間があればぜひご一読してみてください。 佐賀県でも、様々な企業や金融機関等の皆様にご協力いただきつつ、私や福岡支店の調査スタッフが地域の現状について詳しくお話を伺っています。全国の支店網を通じて収集した、こうした「最前線」の情報を本部に集約することで、日本銀行の政策運営の重要な判断材料とさせていただいています。今後とも、どうぞよろしくお願いします。
2025.7.3
よろしくお願いします
6月19日付で佐賀事務所に着任しました加賀山敏郎と申します。日本銀行には1990年に入行し、九州での勤務は、新人時代の大分、前任の福岡に続いて3回目になります。 日本銀行の国内事務所は、現金の円滑な供給・流通、地域の金融・経済情勢の把握、日本銀行の景気判断・政策運営等に関する情報発信、金融経済教育の推進等が主な役割です。微力ではありますが、これまでの職務経験を総動員して、任務に当たっていく所存です。 佐賀県については、コロナ禍前の2019年のGWに唐津・伊万里・有田・佐賀市内と4泊の旅行をして以来、実に多彩な顔を持つ豊かで奥深い土地柄であると感じています。今後も、県内を広く歩き、色々な方のお話を伺いながら、佐賀県についての理解を深めていきたいと思います。皆様、どうぞよろしくお願いします。
2025.6.16
ありがとうございました
6月16日の発令により、本店(東京)に異動することとなりました。在任中を振り返ると、約2年間とは思えないほど、沢山の思い出がよみがえってきます。社会がコロナ禍から正常化し、イベントやお祭りは、これまで以上に盛り上がりました。大イベント「SAGA2024国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会」も、大きな成功を収めました。日本銀行の関係では、2024年7月に新しいお札(日本銀行券)が発行されました。 この間、県内の皆さまには、暖かく迎えていただき、公私ともに、様々な機会に交流、意見交換をさせていただきました。 自然、文化、歴史、お酒・食事、そして人の優しさ・・・佐賀の魅力に感動している間に、あっという間に時が過ぎていった感じがします。 これからも、佐賀とのご縁を大切にし、佐賀の益々の発展を応援したいと考えています。お世話になりました、ありがとうございました。
2025.5.30
佐賀の魅力
佐賀に住んで、早いもので2年になります。この間、仕事に加え、休日はマイカーで、県内のあらゆる場所を訪れてきました。あらためて、佐賀県の地図を眺めると、随分ウロウロしたものだと我ながら思います。この5月だけを振り返っても、10市10町全てに足を踏み入れていますし、主な名所・旧跡では、有田(窯元巡り)、大川内山(同)、小城(蛍鑑賞)、加部島、川古の大楠、玄海エネルギーパーク、佐賀城本丸歴史館、徐福長寿館、大興善寺、多久聖廟、名護屋城跡、菜畑遺跡、浜野浦の棚田、三重津海軍所跡、などを今月は訪れましたが、途中で立ち寄った小さな史跡なども挙げるときりがありません。どこも見応えがあり多くのことを学び感じることができましたが、さらに、施設、お店、駐車場案内など、行く先々で出会った方々は、皆さんとても優しく親切でした。県外からやってきて実感していますが、お世辞ではなく、歴史、文化、自然、食、人、どれをとっても魅力にあふれた県だと思っています。佐賀県の某ランキングの低さなどが時々話題になりますが、私にとっては、まったくもって???です。
2025.5.9
佐賀県の金融経済概況(2025年春)を公表しました
5月7日に、佐賀県の金融経済概況(2025年春)を公表しました。足もとの景気は「横ばい圏内の動きとなっている」と判断しました。前々回(2024年秋・11月)、前回(2025年冬・2月)に続き、3回連続の「横ばい」判断です。 生活に最も関係する「個人消費」は、物価上昇による節約志向が続き、最近はお米の値上がりの影響も聞こえてきますが、全体としては、ハレの日<=特別な日>需要、旅行・観光といった人の動きが活発なこと、給与のアップ等に支えられ、「底堅く推移している」(=下がることなく安定している)状況です。 「給与のアップ」については、人手不足の中、雇用者数が増加し、給与も上昇する動きが当面続くと見られることから、今回「雇用・所得」の判断を引き上げ「改善している」としました。 一方、生産においては、統計(鉱工業生産指数)が、化学や電子部品・デバイスは持ち直し傾向にありますが、ウエイトの大きい食料品を中心に「一段と弱含んでいる」状況を脱していません。また、製造業からは、輸出と関連する企業を中心にアメリカの通商政策の影響を心配する声が上がっています。 アメリカの通商政策については、二転三転する情報に、世界中が先行きを見通し難い状況となっています。結果的に実行される政策の内容は重要なのですが、それ以前に、先が見通せないため、企業や人々が様子見で動かなくなり、経済が停滞することが懸念されます。 見え難い状況ながらも、佐賀県経済への影響などを注視していきたいと思います。
2025.4.18
よく聞く「関税」
このところ、その言葉を聞かない日はない「関税」。所得税や消費税といった私たちが生活する中で支払う税金ではないので、身近には感じ難いものです。「関税」とは、海外からの輸入品に課す税で、輸入者が国に支払っています。どんな影響・効果があるかというと、輸入者は、関税の支払い負担が増えると、その分を販売価格に上乗せするので、輸入品の値段が上がり、同じ物の国産品があれば、関税が高いほど、価格面で輸入品に不利(=国産品に有利)に働きます。これは、国内の産業を保護することが主な目的ですが、不当な貿易政策をとっていると判断した特定の相手国を制裁する目的でも使われます。最近のアメリカは後者を強調していますね。国にとって収入が増える効果もありますが、例えば日本では国税収入に占める関税の割合は1%程度ですし、アメリカも割合は小さいようです。税関のホームページにある関税率表を見ると(私は初めて見てみました)、品目別・国別に、非常に細かく課税の有無、税率が設定されています。緻密な関税の仕組みとは別に、大雑把に高関税策を打ち出すアメリカには困惑させられるばかりです。 今も二転三転する発表に、先行きどうなるかは読み難いですが、佐賀県経済への影響についても、注視していく必要があると考えています。
2025.4.3
短観(2025年3月)が公表されました
4月1日に2025年3月短観(全国企業短期経済観測調査の通称で、「たんかん」と呼ばれています)の結果が公表されました。短観とは、日本銀行が四半期毎に全国の企業(今回の回答企業数8,880社)に実施している統計調査です。 短観については、何度かここでお話ししていますが、今回は、九州・沖縄の短観についてです。日本銀行では、全国版だけではなく、支店や事務所において県や地域単位の調査結果を公表しています。福岡支店が公表した今回の九州・沖縄の短観(回答企業数1,051社)では、業況判断D.I.※は、全産業合計で+20%と前回(12月の調査では+18%)から改善しています。全国では、前回・今回ともに+15%と横ばいだったことと比較すると、プラス幅・動きとも、九州・沖縄は比較的経済が元気な地域と言えるでしょう。背景には、インバウンド需要や都市開発、半導体産業や自動車産業の立地などがあります。 一方で、雇用の質問における、人手が「過剰」(+)と「不足」(-)の回答率の差は、九州・沖縄で-43%の過去最大レベルの不足超幅となっており、全国の-37%と比べて、九州・沖縄は、より人手不足な状況にあります。 先行きについては、関税措置など何をするのか読み難いアメリカの政策の影響も心配されるところです。 ※業況判断D.I.(Diffusion Indexの略)とは、短観を代表する指数です。企業の業況について「良い」「さほど良くない」「悪い」の選択肢で質問し、「良い」と回答した企業の割合から「悪い」の割合を差し引いた数字で表します。
2025.3.17
春の道
この季節、全国でも佐賀県内でも、入学試験、合格発表のニュースを目にします。掲示板の前で喜ぶ姿は、(最近は掲示しない学校も多いようですが)今も昔も風物詩です。また、学生生活を終え社会に出る人達は、新年度を前に、希望と不安を胸に過ごしていることでしょう。 志望していた学校や会社に合格して進む人と、そうでない人、この時点では明暗が分かれたように見えますが、人生はそんなに単純なものではないと思います。 志望して入った学校や会社に大満足、というのが何よりですが、入ってみたら自分に合わなかったとか、逆に、不本意ながら進んだ先で、素晴らしい出会いや打ち込める好きな道を見つけたといった話を山ほど聞いたことがあります。私自身も、不合格などの悔しかった昔の記憶をふと思い出すこともありますが、今となっては独り苦笑いする程度です。 そうした経験から、若い人達に「人生、双六みたいなところもあるから、努力しつつも、振ったサイコロの目でなるようになると思えばいいよ」などと話していたこともあります(若い人は双六なんてしたことないのかもしれませんが)。 「得意淡然 失意泰然」。この季節、冬の次は春だと、前向きにいきたいものです。
2025.2.28
「おかねの作文」コンクール
先日、第57回「おかねの作文」コンクールにおける、「日本銀行総裁賞」の表彰式のため、佐賀大学教育学部附属中学校を訪問しました。 表彰式・受賞作品はこちら(佐賀県金融広報委員会HP)。 このコンクールは、金融経済教育推進機構(J-FLEC <ジェイ・フレック>=Japan Financial Literacy and Education Corporation)が、中学生の皆さんが周囲との会話や、実体験などから得たお金に関する気づきを掘り下げることで、将来の夢の実現やお金への向き合い方を考えるきっかけになることを願い、行っている取り組みです(高校生には小論文コンクールがあります)。 今回は、全国の中学校から5,312作品もの応募があり、その中で、特選5作品(金融担当大臣賞、文部科学大臣賞、日本銀行総裁賞、日本PTA全国協議会会長賞、J-FLEC理事長賞)の一つに選ばれるという快挙でした! 佐賀の若い人達が、様々なことを学び成長していく中で、金融や経済についても関心を持ち、正しい知識を身に付けられるように、私達も注力していきたいと思っています。
2025.2.18
雪・寒波
大雪や寒波のニュースが続いています。日本海側や東北地方などでは、例年の数倍の積雪となる中、建物倒壊、道路の不通、除雪作業中の事故など、被害も出ています。復興途上の能登地方も心配です(地震により道路の消雪装置が壊れて使えなくなっているとの報道も目にしました)。九州も寒波と雪に見舞われ、1~2月は佐賀でも積雪がありましたが、大きな被害はなかったようです。佐賀の穏やかな気候のありがたさを感じつつも、その反面、慣れない積雪や凍結には気を付けないといけません。身近では「雪で機械式駐車場が作動せず、車が出せなかったから次は注意する」という話がありましたが、小さなことでも経験を踏まえて備えることも大切です。
大雪の原因の一つに、日本海の水温が平年より高く、雪の元となる水蒸気が多く供給されることがあるそうです。大型台風と同じく大雪も温暖化が一因とは、環境問題は身近に迫る危機なのだと、改めて思いました。
2025.2.5
佐賀県の金融経済概況(2025年冬)を公表しました
2月3日に、佐賀県の金融経済概況(2025年冬)を公表しました。足もとの景気は「横ばい圏内の動きとなっている」と判断しました。前回(2024年秋・11月1日)公表の際には、「足踏みしている」状態からなかなか抜け出せないので「横ばい圏内」に、判断を半歩下げたイメージです…と説明しましたが、その判断を継続したということです。
個人消費は、節約志向が続いている一方で、年末年始など特別なときには出費を惜しまない消費傾向がみられ、「底堅く推移している」(=下がることなく安定している)状況です。この消費傾向は、ハレの日<=記念日など特別な日>需要とも呼ばれ、お盆やクリスマス、野球の優勝セールなどでも見られました。
また、特別なときといえば、旅行・観光も、秋の行楽シーズン、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の期間、年末年始と好調さを取り戻しています。
生産においては、統計(鉱工業生産指数)が、食料品などを中心に低下傾向を脱しておらず、「一段と弱含んでいる」状況にありますが、世界的なIT関連財の回復に伴い、電子部品・デバイスで上向く動きも伺われます。こうしたことから、佐賀県経済全体が、今後低迷することまではないと考えています。
なお、アメリカの関税発動のニュースが注目されていますが、米国の政策は、先行きの不透明要素なので、佐賀県経済への影響を注視する必要があります。
2025.1.8
2025年(令和7年)もよろしくお願いいたします
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
年明けの佐賀は、穏やかな天候となり、また、年末年始の日並びが連休になり易かったので、遠出された方も多かったのではないでしょうか。私は、大晦日は広大な大詫間で有明海の彼方に沈む夕日を眺め、元旦はベランダから初日の出を拝み、三が日には、佐賀市内のいくつかの神社に初詣しつつ、初売りに立ち寄ったりと、比較的近場でゆっくりと過ごしました。仕事始めからは、唐津や鳥栖など各地にも新年ご挨拶に伺っていますが、皆さん、巳年の本年を脱皮する蛇にかけて「新たに成長する年」と希望を込めていました。
社会が大きく変化する中、先を見通すことは難しい時代ではありますが、本年が、佐賀県が明るい未来へと前進する、成長の年となることを願っています。
日本銀行佐賀事務所は、お札の円滑な供給・流通、金融経済に関する情報発信、地域の経済・金融情勢の把握、金融リテラシー向上に向けた活動などを通じて、佐賀県の発展に貢献できればと考えております。
引き続き、よろしくお願いいたします。
2024.12.24
2024年もお世話になりました
今年(2024年・令和6年)も残すところあと僅かとなりました。毎年、この時期になると1年の短さを感じますが、特に昨年の初夏に佐賀に着任した私にとっては、今年は丸1年を佐賀で過ごし、新しい出会いや新鮮な経験に感動する中で、まさにあっという間に年末を迎えた気がしています。
振り返ってみましょう。アフターコロナの世界で開催された、パリオリンピック・パラリンピックの余韻が続く中、佐賀では、SAGA2024国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会が開催され、国体から進化した新しい大会として、盛り上がりました。準備や付随するイベント・活動も含め、県外の人々に佐賀の魅力を知ってもらい、また、地域をスポーツで活性化する効果もあったと思います。
気候変動や自然災害の影響を実感した年でもありました。夏の猛暑、バルーンフェスタと重なった荒天、8月の日向灘の地震では、佐賀県内も最大で震度4を観測し、初の「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表され、災害への備えの必要性を意識させられました。
日本銀行としては、皆さんのお財布の中でもよく顔を見るようになったと思いますが、7月3日の新しいお札(日本銀行券)の発行がありました。唐津出身の辰野金吾設計の東京駅が新一万円札にデザインされ、唐津市に7番目(AA000007AA)のお札が贈呈されたことも、話題となりました。
日本銀行佐賀事務所は、この1年も佐賀県の皆様方にご理解・ご支援をいただきました。改めて御礼を申し上げます。良いお年をお迎えください。
2024.11.29
続・佐賀の秋
佐賀の秋を満喫しようと、引き続き、県内各地に出向いています。豊かな佐賀の自然に感動しつつも感じたのは、秋の足取りの遅さです。
神埼市の九年庵と仁比山神社は、外国人観光客も含め賑わっていて、歴史的にも興味深い場所で十分に紅葉を楽しめましたが、写真で見るピークの色付きにはまだ到達していない感じでした。鹿島市の中木庭ダム湖畔や、「秋の有田陶磁器まつり」に合わせて訪れた有田町の歴史民俗資料館周辺などの紅葉スポットでも、同じように感じました。少々早めに見に行ってしまった様で、その後、一段と美しさを増したのだろうとは思いますが、従前の感覚だと、ズレてしまうのだな…と実感しました。
「地球温暖化」「異常気象」などと久しく言われていますが、この秋も、残暑が長引いたため、秋物衣料の売上げが伸びなかった時期がありましたし、最近でも海水温が高いことが有明海の県産海苔に影響しているとのニュースを目にするなど、気候は経済・産業にも大きな影響を及ぼします。
佐賀県経済を見ていく上でも、そうした影響にも留意していく必要があると考えています。
2024.11.15
佐賀の秋
11月とはいえ、日中に外を歩くと汗ばむ日もありますが、行楽の秋になったということで、各地を出歩いています。
バルーンフェスタは、最終日の競技と佐賀市内での夜間係留を見ることができました。悪天候によるイベント中止は残念ではありましたが、その中での一部実施は、関係の方々のご尽力によるものだと思います。唐津くんちでは、華麗な曳山巡行を間近に見ることができましたが、小学校校庭の臨時駐車場では丁寧に誘導していただきました。
みやき町の山田ひまわり園では、雨の中、親切に会場まで案内いただき、山々に霧のかかる中に咲く向日葵という、青空の下とは違った美しさを楽しめました。東与賀海岸のシチメンソウは、ここでしか見ることができない、まさに「海の紅葉」ですが、特産品の直売が賑わいを添えていました。
いずれも、素晴らしい観光スポット、観光資源であることは間違いないのですが、様々な場所で感じられる人々の親切さに、楽しさを「追加大盛り」にしていただいていると感じています。
2024.11.6
佐賀県の金融経済概況(2024年秋)を公表しました
11月1日に、佐賀県の金融経済概況(2024年秋)を公表しました。足もとの景気は「横ばい圏内の動きとなっている」と判断しました。2024年冬(2月公表)に「足踏みしている」に判断を引き下げてから、春(4月)、夏(8月)と同じ判断を続けてきましたが、今回、もう一段、判断を引き下げました。
微妙な表現ではありますが、「足踏み」からなかなか脱することができない状態であることを「横ばい圏内」とし、半歩下がったイメージです。
背景としては、個人消費は、物価上昇を受けた節約志向が続き、コロナ後の人々の活動再開による盛り上がりも一巡し、全体としては、力強さに欠ける状況が続いています。こうした中、生産において、物価高の影響による需要の鈍化に台風10号による工場の稼働停止などが加わり、統計上(鉱工業生産指数)も低下を辿っていることから、「弱含んでいる」から「一段と弱含んでいる」としました。
これまた微妙な表現ですが「弱含む」とは、下がり気味の傾向にあり、すぐには上がらなさそう…といったところでしょうか。
もっとも、底堅さを維持している個人消費が所得の上昇などにより持ち直してくることも期待されますし、企業の設備投資は高い水準が見通されています。
荒天によるバルーンフェスタのイベント中止は残念でしたが、秋の行楽シーズンにも期待しつつ、様々な角度から、今後の佐賀県の経済金融情勢を見ていきたいと考えています。
2024.10.15
SAGA2024
SAGA2024国民スポーツ大会は、10月5日に開会し、9月から始まった会期前実施競技を含め、県内各地・県外会場を舞台に熱戦が続いてきましたが、今日15日が閉会式です。
私はSAGAスタジアムの開会式を観覧し、配布された青いTシャツを着て、スタンドの観客とフィールドの選手団がともに盛り上がる一体感を味わうことができました。
国体から国スポに変わる新しい大会をつくることを目指し、これまで関係者の方々が積み重ねてきた準備の上に、選手皆さんの鍛錬の成果が発揮され、素晴らしい大会となったのではないでしょうか。街で都道府県名の入ったウェアの人々とすれ違ったり、試合結果に沸く日々が終わるのは少し寂しいですが、次は10月26日からスタートする「全国障害者スポーツ大会」が待っています。佐賀の熱い秋は、まだまだ続きます。
2024.9.30
佐賀の名月
中秋の名月の9月17日、県内各地でも美しく丸い月を見ることができました。中秋の名月とは、旧暦の8月15日の夜に見える月ですが、「丸い月」としたのは、今年の満月は17日ではなく翌日18日だったからです。このようなズレはよくあることで、今年以降、数年続くそうです。17日の佐賀の最高気温は37.2度、秋とはほど遠い暑さの中、夜空を見上げた方も多かったのではないでしょうか。私は、その数日前、佐賀市星空学習館の定例観望会に行く機会がありました。その夜は空一面を薄い雲が覆っていたのですが、スタッフの方々は何とか楽しんでもらおうと、雲の隙間から見える月に、ドーム内の大きな天体望遠鏡を向けて、クレーターの一つ一つまでハッキリ見える月の姿を見せてくれました。さらに、望遠鏡にスマホをくっつけて写真を撮る方法を教えていただき、図鑑で見るような月面写真を自分で撮影できて、よい記念になりました。参加している子供達も楽しそうで、天体への興味も膨らんだのではないでしょうか。市街地の近くですが、広大な佐賀平野と有明海のお陰で、空の視界が確保されているそうです。こうした大人も子供も好奇心を刺激される環境と施設が身近にあることも、佐賀の魅力の一つだと思いました。
2024.9.4
ナンバー7(AA000007AA)
新しいお札の発行開始(7月3日)から、2か月が経ち、皆さんも徐々に目にする機会が増えてきたのではないでしょうか。
発行開始日には、日本銀行から新しいお札にゆかりのある地方公共団体などに、若い記番号のお札が贈呈されました。九州では、千円札の肖像となった北里柴三郎(1853-1931)の出身地である熊本県の小国町に、新千円札の5番目(AA000005AA)が贈呈されましたが、わが佐賀県においても、唐津市に新一万円札の7番目(AA000007AA)が贈呈されました。唐津出身の「日本近代建築の父」辰野金吾(1854-1919)が設計した東京駅・丸の内駅舎(1914年竣工)が裏面にデザインされているからです。ちなみに、辰野のもう一つの代表作と言われる日本銀行本店本館(1896年竣工)は、過去にいくつかのお札のデザインとなっています。伊藤博文が肖像であった千円札の裏面に描かれていた建物を覚えている方もいるのではないでしょうか。
先日、唐津市において、新一万円札発行の記念講演をさせて頂く機会があり、辰野が監修した旧唐津銀行に展示されている「ナンバー7」を見てきました。ガラスケースに収められた一万円札を見ながら、これが地域の魅力や新しいお札のことを広く知っていただくことに役立つといいな…と思いました。
2024.8.15
猛暑の夏
佐賀に赴任して2度目の夏を迎えました。あまりの暑さに「今年の夏はどのくらい暑いのだろう…」と思い、佐賀地方気象台のホームページを経由して気象庁のデータを見てみると、佐賀の1890年!からの気温をはじめ、膨大な気象データが掲載されていました。
今日は終戦の日です。その日、昭和20年8月15日の佐賀の最高気温は32.3度でした。
今年はというと、7月の月平均気温(29.0度)は同月の観測史上3位、8月5日は観測史上9位の最高気温(38.3度)を記録した日、など、確かに暑い夏です。様々な長期データをパソコンでグラフ化してみると、佐賀における温暖化の進行を見て取ることができます。
夏は夏らしく、冬は冬らしく季節がメリハリをもって巡ることは、経済面では消費に好影響なのですが、暑過ぎて外出を控えるなど、人の動きが鈍ると、経済にマイナスの影響も出てしまうのではないかと心配されます。経済への影響は、県内の経済界の方々などから状況を伺いたいと思っていますが、まずは皆さんの健康第一です。熱中症にはくれぐれも気をつけましょう。
2024.8.5
佐賀県の金融経済概況(2024年夏)を公表しました
8月1日に、佐賀県の金融経済概況(2024年夏)を公表しました。足もとの景気は「回復の動きが足踏みした状態が続いている」と判断しました。前々回(冬:2月6日公表)に「足踏みしている」に判断を引き下げ、前回(春:4月30日公表)は「足踏みした状態が続いている」とし、今回も同様としました。つまり、この半年間「足踏み」が続いていると判断したということです。
その背景ですが、個人消費において、物価上昇を受けた節約志向の消費行動が続いている中、ペントアップ需要(コロナ禍でPent-up=抑制して先延ばしにしていた需要)の盛り上がりも一段落し、消費全体としては、力強さに欠ける状況が続いています。住宅投資も、土地の値上がりや建築コストの上昇を受け、需要はやや弱くなっています。
もっとも、節約一辺倒ではないイベントや記念日などで「お金を使うときは使う」消費の堅調は続いているほか、自動車販売における一部メーカーの工場稼働停止の影響も弱まりました。また、人手不足は深刻な問題ではありますが、その一方で有効求人倍率は高く、所得も上向いています。海外経済の先行きなど、なかなか県内ではコントロールできない不安要素もありますが、「SAGA2024国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会」など、県内が熱く盛り上がるこれから、佐賀県経済も再浮上していくことを期待したいと思います。
2024.7.16
お札(日本銀行券)のユニバーサルデザイン
7月3日発行開始の新しいお札、徐々に皆さんのお手元にも届いている頃でしょうか。前回は、新紙幣の偽造防止技術などについてお話ししましたが、今回は、お札の「ユニバーサルデザイン」についてです。ユニバーサル(Universal)を英和辞典で引くと「全体の、万人の、普遍的な、共通の」などと訳されています。新しいお札には、次のような「どなたにも分かりやすいデザイン」が採用されているのです。
①額面数字(アラビア数字)を大きく、かつ目立つ位置に変更しています、②これまでもあった識別マーク(指で触って券種が分かるマーク)をより分かりやすい形(11 本の斜線)に統一し、券種毎に位置を変えています、③ホログラムとすき入れの形や配置を券種毎に変えています。
年齢、国籍、障がいにかかわらず、券種を識別しやすくする工夫の数々、皆さんも新しいお札を実際に見て、触って、確かめていただければと思います。
最後に繰り返しの注意です。新しいお札の発行に伴う詐欺事件が、既に発生しているというニュースがあります。前のお札も、引き続き通用します。「以前のお札は使えなくなる」などという偽情報や詐欺行為には、くれぐれもご注意ください。
2024.6.28
お札(日本銀行券)が変わります
7月3日水曜日から、新しいお札の発行が始まります。今のお札は2004年(平成16年)11月発行なので、20年ぶりの改刷(絵柄・デザイン変更)です。表面の肖像は、福沢諭吉⇒渋沢栄一(一万円札)、樋口一葉⇒津田梅子(五千円札)、野口英世⇒北里柴三郎(千円札)にバトンタッチされますが、一万円札の裏面には、唐津出身の「日本近代建築の父」辰野金吾(1854-1919)が設計した東京駅・丸の内駅舎(赤レンガ駅舎)が描かれています。改刷の主目的のひとつは「偽造抵抗力」の強化です。コピー機などの印刷技術がデジタル化により著しく高度化している中、偽札を作らせないための数々の最先端技術が用いられています。肖像が立体的に見え、お札を見る角度によって、肖像の顔の向きが回転する「3Dホログラム」、肖像のすかしの周囲に緻密な画線で構成した連続模様を施した「高精細すき入れ」が新たに採用されているほか、従来からの「パールインキ」(お札の左右両端のピンク色の光沢)や、「マイクロ文字」(肉眼では見えないくらいの微小な「NIPPONGINKO」の文字印刷)などなど、多岐にわたる偽造防止技術が搭載されています。
お札を発行し、全国の人々に円滑に行き渡るようにするとともに、皆さんがお札を安心して使えるようにすることは、日本銀行の大きな役割のひとつです。
今回の改刷に際しても、既に全国で約50億枚の新しいお札を備蓄して、態勢を整えていますので、タイミングはバラつきが生じますが、皆さんのお手元に届くのをお待ちください。
最後に一言、現行のお札は新しいお札の発行後も、引き続き通用します。「お札が変わると、前のお札は使えなくなる」などという偽情報や詐欺行為には、くれぐれもご注意ください。
2024.6.17
蛍の里
6月に入り、急に暑さが増してきて、爽やかな初夏はあっという間に過ぎ去った感じですが、佐賀に着任して1年、この季節を待っていました。近場で蛍を見られると聞いていたからです。昨年は転勤の慌ただしさで見逃したので、今年こそはと構えていましたが、「今年は例年より早いようだ」という情報を聞いて、急ぎ6月初に小城市の祇園川を訪れました。日が暮れ、暗くなるにつれて、光がゆらゆらと舞い始め、徐々に増していく様子は、まさに幻想的な風景でした。次の週の観賞会にも参加したので、結局、2回見に行きました。蛍は、10年ほど前に信州のリゾート地で見たのが最後ですが、こんなに沢山の蛍を見たのは初めてです。また、東京では大きなテントの中に蛍を放し、そこに入って観賞するというイベントがあったのですが、長蛇の列で入るのを諦めたことがありました。県の観光サイトを見ると、佐賀、唐津、嬉野、武雄、みやき、有田…と、県内各地の観賞スポットが紹介されていました。こんなに身近に蛍が好む美しい水辺があることは、地元の方には当たり前なのかもしれませんが、大変価値があることだと思います。来年は、もっと情報収集して、県内の蛍の里巡りをしようと、(早過ぎですが)次の初夏へと思いを馳せています。
2024.5.31
高校生パワー
休日の昼間、寛ぎながら、何となくテレビのチャンネルボタンを押していたところ、陸上競技場のトラックを駆け抜けていくランナー達の映像が目に飛び込んできました。現在、県内各地で開催されている、令和6年度・第62回・佐賀県高等学校総合体育大会(県高校総体)の中継でした。プロ競技ではありませんし、知っている選手がいる訳でもありませんが、抜きつ抜かれつの競技自体の魅力と、全力で走る姿に、思わず見入ってしまいました。日頃の練習の成果を出そう、自己ベストを越えようという意気込みは、画面からも伝わってきます。その日の午後遅くには、佐賀アリーナの横をたまたま通り掛かり、学校名を背負った揃いのジャージで帰路につく高校生達をたくさん見かけましたが、(それぞれ勝ち負けはあったのでしょうが)疲れたというより、みんな、まだまだ元気な様子でした。
高校生パワーを目の当たりにしながら思い出したのは、佐賀県の「プロジェクト65+」という高校生の県内就職率65%以上を目指した取組みです。今年4月には3月の卒業者の速報値67%という数字が公表され、上昇傾向にあるようです。佐賀県で育まれた若者のパワーが故郷を発展させる原動力となることは、素晴らしいことだと思います。そしてもちろん、県外から来てくれるパワーも大歓迎です。
2024.5.17
行楽シーズン・おもてなし
「春の行楽シーズン」というのは、いつを指すのだろうかと調べてみたものの、なかなか明確な定義を見つけることができませんでしたが、大体、お花見からゴールデンウィークまでの期間を指すようです。気持ちよく外出できる気候であることも条件だと思いますが、近年は気候変動の影響で、5月半ば以降はかなり暑くなってくるので、この定義は実感にもフィットする気がします。
先日のゴールデンウィーク、私は、有田陶器市、佐賀市周辺のドライブ(道の駅や直売所に立ち寄り)、アウトレットモール、などで過ごしました。どこも賑わっていましたし、駐車場は県外ナンバーも多く混んでいましたが、大渋滞などのストレスはほとんどなく、首都圏で40キロの渋滞を経験してきた身からすると、純粋に行楽を楽しむことができて、大満足でした。そして、ストレスとは反対に印象に残ったのは、有田での、町や店舗の方々の、温かく親切な様子でした。駐車場、シャトルバス乗り場、食事処、陶磁器店などのいずれにおいても、おもてなしの気遣い(ホスピタリティ)を感じました。ある店では「以前お世話になったので、またこの店に来た」という、お客さんと店の方の会話をたまたま耳にしましたが、それも納得できました。観光振興の方策は様々ありますが、その土地が温かく歓迎してくれた思い出は、根っことして大切なことなのだと、改めて思いました。
2024.5.7
佐賀県の金融経済概況(2024年春)を公表しました
4月30日に、佐賀県の金融経済概況(2024年春)を公表しました。足もとの景気は「回復の動きが足踏みした状態が続いている」と判断しました。前回(冬:2月6日公表)、「一時的に回復の動きが足踏みしている」に判断を引き下げましたが、それを据え置いたかたちです。「足踏み」が続いている一番の理由は、個人消費の状況です。物価上昇を受けた消費者の節約志向が続いている中、一部メーカーの工場稼働停止による自動車販売への影響などもあり、消費全体としては、力強さに欠ける状況が続いています。
もっとも、節約志向がますます強まっている訳ではなく、人々もお金を使うときは使っていて、イベントや記念日、旅行・観光などに関する消費は堅調です。また、有効求人倍率は高く、所得も上向いている中で、今後の賃上げ期待も広がっています。これらに支えられ、県内の個人消費、そして景気全体が、足踏みから抜け出していくことが期待されます。
2024.4.15
第200回全国企業短期経済観測調査(2024年3月)
4月1日に2024年3月短観(全国企業短期経済観測調査の通称)の結果が公表されました。短観とは、日本銀行が四半期毎に約1万社の企業を対象に実施している統計調査です。今回は第200回調査で、ほぼ現在のかたちの調査となった1974年(昭和49年)から、50年の節目を迎えました。短観が長きにわたり、景気・企業動向を見る代表的な統計であり続けているのは、約1万社からの回答率が毎回99%超!という、企業の皆様の御協力のお陰です。改めまして、御礼申し上げます。
調査の結果ですが、注目度が高い大企業の業況判断D.I.※は、製造業は、一部自動車メーカーの生産・出荷停止の影響などにより、+11%(前回12月の調査では+13%)と4四半期ぶりに悪化しました。非製造業は、値上げ(価格転嫁)が進んでいることや、訪日外国人の増加(インバウンド需要)などにより+34%(前回は+32%)と改善し、バブル景気以来の高いレベルに達しています。こうした中、人手不足が益々深刻化しています。従業員が不足しているとの回答割合は、一段と高まり、これもバブル期以来となっています。人手不足は賃金の上昇(人件費増加)に繋がりますが、これが価格に転嫁され、物価と賃金がバランスよく上昇していくかが、今後注目されます。
※業況判断D.I.(Diffusion Indexの略)とは、短観を代表する指数です。企業の業況について「良い」「さほど良くない」「悪い」の選択肢で質問し、「良い」と回答した企業の割合から「悪い」の割合を差し引いた数字で表します。
2024.3.29
ゆく年度くる年度
佐賀でも桜の開花が遅れているようで、新年度(2024年度・令和6年度)は、満開の桜を見上げながらのスタートとなりそうです。年度替わりは、進学、進級、転勤、転職、部署異動、などなど別れと出会いの季節です。私自身は、昨年の5月に東京から佐賀に転勤してきて、故郷(長崎)に近く、自然も文化も豊かな土地で、皆さんに優しく迎えて頂いたので、あまり(全然)寂しくなかったのですが、約30年前のインターネットもない時代に九州から上京したときの希望と不安の入り混じった気持ちは、昨日のように思い出せます。その後、何度も自分自身と周囲の人々の異動・転勤を経験して慣れっこになっていましたが、佐賀に来て人との関係が濃くなったせいか、最近は転勤のご挨拶を頂くと、寂しく感じるようになりました。
佐賀で生まれ育って県外に出る人から、短い期間で佐賀を離れる人まで、様々でしょうが、離れて分かる故郷佐賀の良さが沢山あると思いますし、短くても一時期を過ごした佐賀の思い出を忘れないで頂きたいと思います。
そして、新年度には、佐賀に進学、赴任してくる人達がいます。私もまだ新参者ではありますが、今度は、そうした方々に佐賀の楽しさ、美味しさ、奥深さを(先輩ぶって)お伝えしようと、今から楽しみにしています。
2024.3.15
雛祭り・ひな・ひいな
3月といえば、雛祭り。佐賀市では「佐賀城下ひな祭り」が開催され、私もレトロな建物の中に飾られた美しいお雛様を見に行きました。以前、県外の方から「『ひいな祭り』と呼ぶ地域があるけれど、佐賀はどうですか?」と聞かれました。調べてみると、京都の市比賣(いちひめ)神社の「ひいなまつり」が有名なほか、大分の杵築市の「ひいなめぐり」や、新潟の「絵紙と小千谷のひいな祭り」などがありました。県内でも「唐津のひいな遊び」では市内に古くから伝わる雛人形を、「有田雛( ひいな) のやきものまつり」では磁器のお雛様を、街中を巡って楽しめる華やかな行事があります。ひなまつりの源流は、諸説あるようですが、古くは人形を「ひいな」と呼び、貴族の子供の「ひいな遊び」が江戸時代に雛祭りに変わっていったそうです。人形が主役のイベントなので、古式ゆかしく「ひいな」と呼んでいるのだろうと思いましたが、確かに春を感じさせる優雅な響きのように(何となく)感じます。
2024.2.29
延暦15年・慶長2年
先日、梅の名所として名高い、小城市の牛尾梅林を訪れました。2月上旬だったので、まだ梅は咲き始めでしたが、その代り、人出は少なかったので、満開になったときを想像しながら、ゆっくりと散策することができました。梅林のある丘には、菜の花も咲いていて、天気がよかったので、丘の上からは、眼下に佐賀平野を見渡せました。
のんびりと歩いて行くと、丘を少し下りたところに、牛尾神社があります。創建は延暦15年(796年)とのこと、なんと、あの「鳴くよ(794)ウグイス」の平安京遷都から2年後、平安時代の初めです。そして境内には、県内最古級の肥前鳥居が建っていて、柱には、うっすらと慶長2年(1597年)の銘を読むことができます。慶長2年といえば、名護屋城を拠点とした「慶長の役」開戦の年(翌年、豊臣秀吉が死去し撤退)であり、そして、鳥居はこの戦に出征した初代藩主・鍋島勝茂公が奉納した鳥居とのことです。梅を見に行ったはずが、またも、佐賀の歴史に思いを馳せる一日となりました。
2024.2.6
佐賀県の金融経済概況(2024年冬)を公表しました
本日、佐賀県の金融経済概況(2024年冬)を公表しました。足もとの景気は「一時的に回復の動きが足踏みしている」と判断しました。これまで、夏(8月1日公表)に「緩やかに回復している」に判断を引き上げて、秋(11月1日公表)も同じ判断を継続していたので、半年ぶりの判断変更です。判断を引き下げた主な理由は、個人消費の回復が一時的に鈍っていることです。コロナ後、人々の動きが活発になり、お金を使い始め、求人の増加や賃金の上昇も、消費を後押ししています。一方で、皆さんも実感されているように物価が上昇しているので、節約志向が広がってきています。佐賀県では、足もと、節約の影響が一部の商品の売上高に現れているようなので、個人消費の判断は「物価上昇の広がり等から、一時的に回復の動きが足踏みしている」と判断しました。
もっとも、設備投資や雇用・所得などは上向いているほか、人々も節約一辺倒ではなく、使うときは使うメリハリのある消費行動をしています。なので、これから景気が下り坂になるとまでは考え難く、足踏みから、再び前進していくことを期待しています。
2024.1.9
2024年もよろしくお願いいたします
年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
また、この度の能登半島地震により、被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。
今年は、災害・事故が相次ぐ年明けとなりましたが、新型コロナ5類移行後初めてのお正月ということで、帰省や初詣など、人出はかなり多かったようです。
私も三が日の間に、佐嘉神社などいくつかの神社に行き、松原神社では拝殿の輝く龍の彫刻を拝見しました。
今年の干支は甲辰(きのえたつ)ということで、新しいことをはじめて成功する年、これまで準備してきたことが実を結ぶ年、と言われています。SAGA2024国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催など、本年が新しい佐賀県への、さらなる飛躍の年となることを願っています。
本年も、日本銀行佐賀事務所は、お札の円滑な供給・流通(7月には、20年ぶりに新しい日本銀行券が発行されます)、金融経済に関する情報発信、地域の経済・金融情勢の把握、金融リテラシー向上に向けた活動などを通じて、佐賀県の皆さまのお役に立てればと考えております。
引き続き、ご理解・ご支援をよろしくお願いいたします。
2023.12.28
2023年もお世話になりました
今年(2023年・令和5年)が終わろうとしています。振り返ると、決して平穏な年ではありませんでしたが、世の中全体の変化としては、やはり、2020年春頃の第1波から、3年以上にわたって、私達の行動を制約してきたコロナ禍からの正常化ではないでしょうか。感染症法上の5類移行(5月)後、人々の動きが徐々に活発化し、コロナ前の生活が戻ってきました。もちろん、感染症がなくなった訳ではないので注意は必要ですが、夏休み、秋の行楽、お祭りなど様々な行事に「コロナ後初めての」の前置きがつけられ、バルーンフェスタは累計90万人を超える人出でした。そして、この正常化のタイミングで、SAGAアリーナがオープンし、B1のバルーナーズ、V1のスプリングスの試合や様々なイベントが盛り上がりを見せています。
人が動くと、消費に繋がり、消費は企業の売上げに繋がり、売上げは給与増に繋がり、給与増は、消費に繋がります。佐賀県内の景気も、このサイクルが回り始めていますが、これがしっかり続くかは来年が勝負となるでしょう。
日本銀行佐賀事務所は、この1年も佐賀県の皆様方にご理解・ご支援をいただきました。改めて御礼申し上げます。どうぞ良いお年をお迎えください。
2023.12.15
短観(2023年12月)が公表されました
12月13日に2023年12月短観の結果が公表されました。短観(たんかん)とは「全国企業短期経済観測調査」の通称で、日本銀行が四半期毎に約1万社の企業を対象に実施している統計調査です。調査の中で注目度が高い大企業の業況判断D.I.※は、製造業は、部品(半導体)不足が解消し生産が回復している自動車産業に牽引され、+12%(前回9月の調査では+9%)と3四半期連続で改善しました。非製造業は、コロナ後の人の動きの活発化、訪日外国人の増加(インバウンド需要)などにより+30%(前回は+27%)と改善し、約32年ぶり(バブル景気の頃)の高いレベルに達しています。製造業・非製造業ともに幅広い業種で改善していて、値上げ(価格転嫁)が進んでいることも業況改善を後押ししています。一方で、短観の質問に「人手不足」と回答した企業の割合は過去最高レベルとなっていて、さらに深刻化しているほか、物価高が続く中で人々に節約志向が広がっているとの声も聞かれていて、これらが景気に与える影響は、注意して見ていく必要があります。
※業況判断D.I.(Diffusion Indexの略)とは、短観を代表する指数です。企業の業況について「良い」「さほど良くない」「悪い」の選択肢で質問し、「良い」と回答した企業の割合から「悪い」の割合を差し引いた数字で表します。
2023.11.30
九州佐賀国際空港
今週、出張があり、佐賀空港(九州佐賀国際空港)を利用しました。いつもながら、空から見る有明海の美しさ、便利で快適な空港施設、市街地へのスムーズなアクセスが嬉しく、とても好きな空港です。
国土交通省が公表している「空港管理状況調書」という資料があります。最新は2022年のデータですが、コロナの影響がない2019年(令和元年)の数字と国内空港における順位をみると、佐賀空港は、乗降客数:81万人(38位)、着陸回数:0.5万回(40位)となっています。両隣の福岡空港は2,468万人(4位)・9.1万回(4位)、長崎空港は336万人(14位)・1.6万回(14位)でした。
佐賀空港にとって、今年は、開港(1998年)から25周年、利用者1000万人到達の節目の年となりました。現在、滑走路の延長が計画されていますが、延長を待たずとも、佐賀空港の魅力を、過密で有名な福岡空港利用者を含む周辺エリアの方々にもっと知ってもらい、北部九州の人の往来の拠点として、佐賀県の発展を後押ししていくことを願っています。
2023.11.15
豪華イベントはしご
11月の三連休の佐賀県は、好天に恵まれ、夏に戻ったような陽気でした(11月の観測史上最高気温を更新した地点もいくつかありました)。そうした中、県内では、様々なイベントがコロナ前と同じ形で開催されました。
4年ぶりの海外選手本格参加となった「2023佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」。朝6時の列車で佐賀駅を出発し、競技スタートの一斉離陸を観に行きました。バーナーの炎を受けてバルーンがムクムクと立ち上がり、澄んだ空に次々と浮上する壮観な景色には、圧倒されました。そして、午後からは、唐津へと移動し、30数年振りに観る「唐津くんち」へ。曳山巡行と、全ての曳山が西の浜御旅所に一堂に揃った姿を観ましたが、(ユネスコ無形文化遺産である伝統文化なので当然ではありますが)昔の記憶そのままの、華やかで勇壮なお祭りでした。そして連休最終日には、バルーンの感動をもう一度味わいたくて、自転車を走らせ、フェスタの最後を飾る夜間係留(ラ・モンゴルフィエ・ノクチューン)の、幻想的な世界を楽しみました。佐賀の魅力(の一部)を堪能した、とても充実した三連休でした。
2023.11.1
佐賀県の金融経済概況(2023年秋)を公表しました
本日、佐賀県の金融経済概況(2023年秋)を公表しました。足もとの景気は「緩やかに回復している」と判断し、前回の夏時点(8月1日公表)と同様の判断としています。夏に判断を引き上げてからの継続なので、景気が回復を歩んでいる方向に向かっていることには変わりありません。コロナ後初めての夏休みシーズンはイベントなども通常開催に戻り、人の動きも活発になりました。これに伴い、個人消費が回復し、雇用・所得情勢も賃金の上昇がみられ、緩やかに改善しています。旅行・観光需要も、イベントや西九州新幹線効果に加えて、訪日外国人の需要(インバウンド需要)もあって、増加しています。もっとも、中国をはじめ減速気味の海外経済は、戦争・紛争なども含め、不確実性が高まっていますし、物価上昇や人手不足の影響も気になります。こうしたリスクに留意しながら、今後の当地の経済金融情勢を見ていく必要があると考えています。
2023.10.16
国スポ・全障スポまで1年
現在、鹿児島県では、「燃ゆる感動・かごしま国体」が開催されており、佐賀県勢の活躍も連日報じられています。そして、1年後2024年10月には、佐賀県において「SAGA2024国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会」が開催されます。1976年(昭和51年)の「若楠国体」以来の佐賀での開催ですが、今回は、国体(国民体育大会)から国スポ(国民スポーツ大会)に変わる初めての大会ということで、多くの新しい取組みが企画されているようです。社会におけるスポーツの価値が広く認められるようになった今の時代に相応しい、新たなスポーツの祭典を楽しみにしつつ、開催地県民としての参加者の意識も持って、大会を盛り上げていきたいものです。
2023.9.29
武雄温泉駅で待ち合わせ
先日、十数年振りに会う長崎在住の友人と武雄温泉駅で待ち合わせ、食事とミニ観光をしました。私の住む佐賀市と長崎との間の地を検討し、武雄としました。長崎の友人は、当初は在来線で佐賀方面に来ようとしていたのですが、普段マイカー利用ばかりなので、新幹線が開通した後の列車ダイヤを初めて見たらしく、減便を知って驚いていました。その一方で、乗車した新幹線が武雄まであっという間に到着するスピードを体感して驚いてもいました。ちょうど新幹線開業1年のタイミングでの出来事でしたが、便利と不便の両面のバランスの難しさを実感しました。武雄温泉では、楼門や新館を訪れました。これらは、前々回にお話した辰野金吾の設計ですが、東京駅や日本銀行本店とはまったく異なる、同じ人の作品とは思えない、竜宮城のような世界を創り上げています。東京駅のドーム天井を飾る8つの干支のレリーフと、楼門の天井にある4つの干支の彫絵を合わせて十二支が揃うそうですが、いつか彫絵の実物を見たいと思いながら、夕方の武雄を後にしました。
2023.9.15
災害に備えましょう
9月1日は「防災の日」ですが、今年は、関東大震災(1923年<大正12年>9月1日午前11時58分、マグニチュード7.9)から100年目の節目の日でした。長らく東京に住んでいた私としては、佐賀での揺れを感じることがない日々に、地震の少なさを実感しています。しかし、ゼロではありません。福岡県西方沖地震(2005年3月)や、熊本地震(2016年4月)では、県内の一部で強い揺れがあったことを憶えている方もいるかと思います。豪雨、台風については、近年、県内でも被害が頻発し、警戒感は高まっているでしょうが、それでも身近に被害がなければ、なかなか危機感は湧かないものです。しかし、備えや心構えの少しの差が、生死を分けることもあるのです。防災関連の報道や痛ましい災害のニュースを見て「もしも自分に災害の危険が迫ったら」を具体的に想像し、防災意識を高め、備えておくことが大切だと思いました。
日本銀行では、災害が発生した場合にも、お金の円滑な流通などの責務を果たせるように、業務継続体制の整備に努めています。
2023.8.31
旧唐津銀行(辰野金吾記念館)
先日、旧唐津銀行において「辰野金吾と日本銀行」という題で講演をさせて頂きました。旧唐津銀行は「日本近代建築の父」である辰野金吾(1854-1919)監修・弟子の田中実(1885-1949)設計による建物(1912年竣工)で、1997年まで佐賀銀行唐津支店として使用されていた、県の重要文化財です。辰野は、日本銀行本店(1896年竣工)や東京駅(1914年竣工)が代表作ですが、旧唐津銀行は、東京駅と同じ辰野式と呼ばれるレンガ造りの優美な建物です。辰野は、唐津藩の洋学校「耐恒寮」で学びましたが、同校には、東京丸の内のオフィス街の建物群を設計した曽禰達蔵(1852- 1937)や、辰野のもとで日本銀行本店の建設に携わり、軽井沢の旧三笠ホテル(国指定重要文化財)を設計した岡田時太郎(1859- 1926)も同時期に在籍していました。唐津で切磋琢磨した若者達が、その後、揺籃期の日本建築界をリードしたことは、とても誇らしいことだと思います。
辰野・曽禰の二人の像が、旧唐津銀行前と佐賀銀行本店の前にあります。
2023.8.15
夏の高校野球
第105回全国高等学校野球選手権記念大会では、佐賀県代表・初出場の鳥栖工業高等学校が、1回戦を見事に突破、昨日(14日)の2回戦は接戦の末惜敗しましたが、選手皆さんの健闘を讃えたいと思います。
去る7月23日、佐賀県大会の準決勝を観戦に、さがみどりの森球場へ行きました。広大な県立森林公園の中にある、文字どおり緑に囲まれ、天然芝のグラウンドは広く(グラウンド面積は甲子園より広い)、観客席も快適な素晴らしい球場でした。試合は手に汗握る展開で延長戦となり、タイブレークを初めて目の前で見ました。選手も応援席も一生懸命、駐車場の誘導でも高校生が頑張っていて、多くの方々が力を合わせ、大きな大会が運営されていることを実感しました。
今日8月15日は終戦の日。例年、甲子園でも正午には試合を中断して黙祷が行われます(本日は台風により試合中止)。安心してスポーツで競い、楽しめる平和な世界を心から願います。
2023.8.1
佐賀県の金融経済概況(2023年夏)を公表しました
本日、佐賀県の金融経済概況(2023年夏)を公表しました。足もとの景気は「緩やかに回復している」と判断し、前回の春時点(5月9日公表)から判断を引き上げています。個人消費が回復しているほか、設備投資の大幅な増加が続く中で、雇用・所得情勢が緩やかに改善しています。個人消費においては、経済活動の再開によって人の流れも増え、いわゆるペントアップ需要(コロナ禍でPent-up=抑制して先延ばしにしていた需要)が、モノ・サービスの両方で出てきています。旅行・観光需要も、全国旅行支援やイベント効果もあって、増加しています。もっとも、物価動向が個人消費や企業収益に与える影響や、海外経済の減速の影響などには留意しながら、今後の当地の経済金融情勢を見ていく必要があると考えています。
2023.7.18
短観(2023年6月)が公表されました
7月3日に2023年6月短観の結果が公表されました。短観(たんかん)とは「全国企業短期経済観測調査」の通称で、日本銀行が四半期毎に約1万社の企業を対象に実施している統計調査です。調査の中で注目度が高い大企業の業況判断D.I.※は、製造業で原材料価格の上昇が落ち着く中、販売価格の引上げが進んでいることなどから、+5%(前回3月の調査では+1%)と改善しました。また、非製造業でもコロナ禍で控えられていた買物・外出・外食の回復などにより+23%(前回は+20%)と改善しています。ただ、景気が回復しつつあることに伴い、全国的に人手不足感が強まり、事業に影響が出ているとの声も聞かれていて、景気の足を引っ張ることにならないか、注意する必要があります。
※業況判断D.I.(Diffusion Indexの略)とは、短観を代表する指数です。企業の業況について「良い」「さほど良くない」「悪い」の選択肢で質問し、「良い」と回答した企業の割合から「悪い」の割合を差し引いた数字で表します。
2023.6.30
吉野ケ里フィーバー
先日、吉野ケ里歴史公園を訪れました。4月に「謎のエリア」なる丘で石棺墓が発見され、6月の内部調査では、期待された副葬品こそ見つからなかったものの、今熱い注目を集めている地です。公開日ではなかったので、発掘現場は見ていませんが、緑豊かで広大な公園を気持ちよく歩きました。私が前にこの地に来たのは、平成になったばかりの吉野ケ里フィーバーの時でした。世紀の発見のニュースに、福岡からバイクで脊振の山を越えて、土が剥き出しの発掘現場を見学に来ました。途中、桜が満開で美しかった記憶もあります。あれから30数年、色々なことがあったなぁと感慨に耽るのも束の間、発見された石棺墓は約1800年前のものと推定され、また、このエリアには1万2000年前には人が住んでいたとのこと。悠久の時の流れの中では、30数年など一瞬のちっぽけなものだと、別の意味でも心がゆったりと癒されました。
2023.6.12
よろしくお願いいたします
5月29日付で日本銀行佐賀事務所長に着任しました西崎淳一と申します。当事務所の役割である、お札(日本銀行券)の円滑な供給・流通、金融経済に関する情報発信、地域の経済・金融情勢の把握、金融知識の向上に向けた活動などを通じて、佐賀県の社会・経済の発展のために少しでもお役に立てればと思っております。また、日本銀行の窓口として、県内各地をお訪ねし、皆様と交流させていただきながら、豊かな自然、古代から続く歴史と文化、美味しい産品などなど、たくさんの佐賀県の魅力を実体験し、様々な場で紹介していきたいと思います。引き続き、当事務所ともども、よろしくお願いいたします。
2023.5.22
ありがとうございました
5月22日付で異動することになりました。2021年6月に当事務所に着任し、約2年間を佐賀で過ごしました。着任後、暫くの間は、感染症の影響が続く中、様々な制約の下で、当事務所の活動を進めていくこととなりましたが、2022年半ば辺りからは感染症抑制と経済活動の両立が進む中で、佐賀県内も徐々に日常を取り戻し、活動を円滑に進めていくことができました。また、仕事以外の面でも、佐賀インターナショナルバルーンフェスタ、唐津くんち、有田陶器市、吉野ケ里遺跡などを訪れ、充実した生活を送ることもできました。改めて御礼申し上げます。先日、SAGAアリーナがオープンし、2024年には「国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会」が開催されます。佐賀県が今後、益々発展し、成長していくことを楽しみにしております。当事務所の活動に対して引き続きご理解・ご支援をいただけると幸いです。
2023.5.9
佐賀県の金融経済概況(2023年春)を公表しました
本日、佐賀県の金融経済概況(2023年春)を公表しました。足もとの景気は「持ち直している」と判断しています。個人消費が着実に持ち直しているほか、設備投資の大幅な増加が続く中で、雇用・所得情勢が緩やかに改善しています。個人消費については、経済活動の再開に伴う人流の改善、全国旅行支援やインバウンド、西九州新幹線が押上げに寄与し、旅行・観光が着実に持ち直しを続けているほか、コンビニエンスストアなどでの財消費も一段と改善しています。もっとも、最近の物価上昇については、家計の実質所得や企業収益に対する下押し要因として作用しているほか、海外経済についても、回復ペースが鈍化しています。こうした点が当地の経済金融情勢に与える影響については、引き続き留意していく必要があると考えています。
2023.4.20
佐賀県立美術館
「佐賀県立美術館(佐賀市)」を訪れました。この美術館では、佐賀県出身の日本近代洋画の巨匠・岡田三郎助の作品などが常設展示されています。明治期の画家としては黒田清輝がよく知られています。私自身も岡田三郎助のことは、この美術館を訪れるまで知りませんでしたが、岡田は黒田とも親交があり、東京美術学校(現東京藝術大学)の教授を務めたほか、第1回文化勲章も受章しています。また、この美術館の見どころの一つは「岡田三郎助アトリエ」です。これは岡田が東京に建てたアトリエを移築復原し、公開しているものです。明治時代のアトリエで、当初の姿で今日まで残されている例は他に確認されていないそうです。常設展示は、年間数回程度、展示作品の入れ替えが行われているとのことですので、これからも訪れたいと思います。
2023.4.10
短観(2023年3月)が公表されました
4月3日に2023年3月短観の結果が公表されました。短観は日本銀行が四半期毎に約1万社の企業を対象に実施している統計調査です。注目度が高い大企業の業況判断D.I.は、製造業が+1%、前回調査(12月)比▲6%ポイントの悪化となった一方、非製造業が+20%、同+1%ポイントの改善となりました。製造業では、原材料・コスト高の影響や海外経済の減速などを背景に業況が悪化しています。一方、非製造業では、感染症の影響緩和、全国旅行支援の効果、インバウンド需要の増加などを背景に業況が改善しています。先行きについては物価高や人手不足などを懸念する声が聞かれています。こうした点が経済活動に与える影響については、引き続きよくみていく必要があると考えています。
2023.3.31
佐賀城下ひなまつり
「佐賀城下ひなまつり(佐賀市)」が2月11日から3月21日の日程で開催されました。このまつりは、感染症の影響もあって3年振りの開催となるそうです。開催期間中は、徴古館や佐賀市歴史民俗館をはじめ市内各所で、ひな飾りが展示されたほか、656広場などでは様々なイベントも開催されていました。私自身も市内各所で展示されているひな飾りを見て回りましたが、普段はあまり見かけることがないグループや家族づれで街中を歩く姿が見られました。県内では「さが桜マラソン2023」や「鹿島酒蔵ツーリズム」も4年振りに開催されています。来年度にかけてこうした様々なイベントが再開され、県内各地に賑わいが戻ってくることを期待しています。
2023.3.20
金融広報アドバイザー
3月10日付のちょっと一言で、「佐賀県金融広報委員会」について、お話しさせて頂きましたが、今回はその続きです。佐賀県金融広報委員会では、金融や経済に関する情報提供や、学校などでの金融・金銭教育活動の支援を行っていますが、これらの活動を実際に担っているのが「金融広報アドバイザー」です。同委員会では、金融・金銭教育や生活設計の第一線で活躍している方々にアドバイザーを委嘱し、学校の授業、大学の講義、公民館や地域サークルの講座・学習会などの講師として派遣しています。現在、佐賀県では15名の方が同アドバイザーとして活動しています。講師派遣をご希望される方は同委員会の事務局(佐賀県くらしの安全安心課内)までご相談ください。
2023.3.10
佐賀県金融広報委員会
「佐賀県金融広報委員会」ってご存じでしょうか?佐賀県金融広報委員会は、佐賀県、佐賀財務事務所、日本銀行佐賀事務所、民間金融機関、民間団体などが協力し、県民の皆様に中立・公正な立場から、暮らしに身近な金融や経済に関する情報提供や、学校などでの金融・金銭教育活動の支援を行っている組織です。事務局は佐賀県くらしの安全安心課内にあります。具体的な活動内容としては、「金融広報アドバイザーの派遣」、「金融・金銭教育研究校への支援」、「講演会やセミナーなどのイベント開催」、「ホームページや刊行物による情報提供」などを行っています。当事務所もこうした活動を通して県民の皆様の金融リテラシー(金融や経済に関する知識・判断力)向上のためのお役に立てればと考えています。
2023.2.28
ふたつ星4047
JR九州が運行している列車「ふたつ星4047」に乗車しました。この列車は武雄温泉駅と長崎駅の間で運行されている観光列車です。私は江北駅で乗車し、長崎駅まで利用しました。武雄温泉駅と長崎駅の間は、西九州新幹線を利用すると約30分ですが、この列車は約3時間をかけて長崎本線を移動します。列車内では有明海などの景色を楽しみながらお酒や食事を楽しむことができました。また、肥前浜駅などの停車駅では短時間ではありますが地元の方々と交流することもできました。列車は単なる移動手段としてだけではなく、列車内で過ごす時間を楽しむこともできます。佐賀県内でも多くの在来線が運行していますので、これからも列車を利用して、様々な楽しみ方ができればと思っています。
2023.2.20
事務所開設77周年
2月18日、当事務所は開設77周年を迎えました。当事務所は、1946年、当時の佐賀中央銀行佐賀支店(元佐賀銀行呉服町支店)内に開設され、その後幾度かの移転を経て、現在は佐賀銀行本店内で営業しています。現在の事務所は、佐賀銀行本店の新築とともに1975年10月から今の建物で営業していますが、翌年1976年2月には近隣地で大きな出来事がありました。JR佐賀駅の移転です。高架化工事の完成により駅が約200 m北側に移転しました。従って、当事務所が今の建物で営業を開始してから数か月間は、当事務所は佐賀駅の近くで営業していたことになります。当時はまだ中央大通りにアーケードが存在していた時期でもあり、当事務所の前も多くの人で賑わっていたのではないでしょうか。
2023.2.10
祐徳稲荷神社
「祐徳稲荷神社(鹿島市)」を訪れました。この神社は日本三大稲荷の一つに数えられ、佐賀県内の代表的な観光地の一つです。境内は、楼門や、117段の階段を上った舞台造りの上に建てられた本殿などで構成され、九州の日光東照宮とも言われているそうです。私は本殿からさらに足を延ばし、山頂にある奥の院まで行きましたが、ここから眺める鹿島市内から有明海へと続く景色は素晴らしかったです。当日は、JRとバスを利用して、祐徳稲荷神社のほか、肥前浜宿(酒蔵通り)などを見て回りました。JR肥前浜駅では列車の待ち時間を利用して、日本酒を堪能することもできました。佐賀県は、魅力ある観光地同士が近くに所在していることも多いため、公共交通機関を利用して、お酒を楽しみつつ短時間で観光を楽しむことができます。こうした点も佐賀観光の魅力の一つだと思います。
2023.1.31
佐賀県の金融経済概況(2023年冬)を公表しました
本日、佐賀県の金融経済概況(2023年冬)を公表しました。足もとの景気は「持ち直している」と判断し、前回の秋時点から判断を引き上げています。個人消費が持ち直しているほか、高水準の公共投資や設備投資の増加が続く中で、雇用・所得情勢が緩やかに改善しています。個人消費については、経済活動の再開に伴う人流改善に、西九州新幹線の開業効果や、全国旅行支援の効果も加わり、旅行・観光が持ち直しを続けているほか、コンビニエンスストアなどでの財消費も増加しています。もっとも、最近の物価上昇については、家計の実質所得や企業収益に対する下押し要因として作用しているほか、海外経済についても、回復ペースが鈍化しています。こうした点が当地の経済金融情勢に与える影響については、引き続き留意していく必要があると考えています。
2023.1.20
銀行券発行残高125.1兆円
2022年(令和4年)末時点で流通している銀行券(お札)の残高は125.1兆円でした。日本では、近年、決済のキャッシュレス化が進展していますが、一方で、銀行券の残高も増え続けています。日本は諸外国と比べても銀行券への需要が強い国と言われており、例えば、銀行券の残高の対名目GDP比率は米国が10%弱のところ、日本は20%強の水準に達しています。日本で銀行券需要が強い背景としては、治安がよく盗難が少ないこと、偽造の発生が少なく安心してお札を使えること、金融機関の店舗やATMなど現金を授受するためのインフラが整っていることが挙げられます。佐賀県では2022年中に日本銀行から4,044億円の銀行券が支払われました。当事務所では引き続き銀行券の安定的な供給に努めてまいります。
2023.1.10
2023年も宜しくお願い申し上げます
新年明けましておめでとうございます。新たな年を迎えることとなりました。2023年の干支は卯(うさぎ)です。うさぎは「跳ねる」ため、卯年は経済や企業にとって縁起の良い年とも言われているようです。本年が佐賀県経済にとって飛躍の年となることを期待しています。当事務所では本年も県民の皆さま方との信頼関係を大切にし、お札の安定的な供給、金融経済や日本銀行の活動に関する情報発信などを通じて、皆さま方のお役に立てればと考えております。私どもの活動に対して引き続きご理解・ご支援をいただけると幸いです。事務所職員ともども本年も宜しくお願い申し上げます。